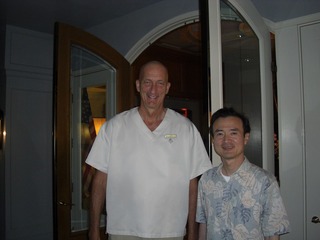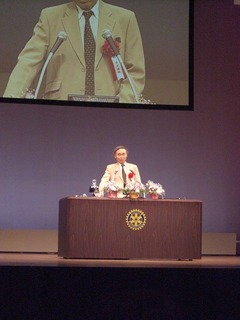Home > Archives > 2009年11月 Archive
2009年11月 Archive
日銀本店
- 2009年11月29日 18:07
先日、日本銀行本店と貨幣博物館を見学する機会が
ありました。重要文化財に指定されている日銀の本館は
地上3階、地下1階の石積み煉瓦造りで明治29年の完成です。
日銀は明治15年に現在の日本橋箱崎町で開業しましたが
手狭になり、もともと江戸時代に小判などの金貨を鋳造していた
「金座」の跡地だった現在の敷地を購入したそうです。
設計者は東京駅の駅舎などの設計をした辰野金吾で
海外視察をしたあと、ベルギーの中央銀行をモデルに
ネオバロック様式の建物を計画しました。
「日銀」と聞くとすぐ紙幣の印刷と連想してしまいますが
本来の使命は「物価安定のための金融政策を行なうこと」だそうで
毎日金融機関との国債などの売買を通して
世の中に出回る資金や金利を調整しています。
確かにインフレ(物価が上がりお金の価値が下がる)でも
デフレ(物価が下がりお金が使われず不景気になる)でも
私たちの生活は苦しいものになり、その安定が第一目的なのです。
2階廊下には歴代の日銀総裁のいかめしい肖像画が掛けてあります。
中には小磯良平のような著名な画家によるものもありましたが
少し前から世相を反映して?予算の関係で作成は中止、白川さんのはありません。
お土産に古いお札を裁断したチップをもらいましたが
1万円札が4~5年、千円札が1,2年で回収することを聞き
お金の流通の激しさに驚きました。
向かいの貨幣博物館では、奈良時代の「和同開珎」から
現代までの変遷が学べます。16世紀までは中国銭が多く流通し
特に粗悪なものを鐚(びた)銭と呼んだそうです。
「びた1文、まけられない」がここから来ているとは知りませんでした。
また秀吉が作らせた「天正大判」は現在3000万円はするとのこと。
何となく遠い存在だった日銀が身近に感じた一日でした。
(社長)
ラナイ島の旅 (2)
- 2009年11月20日 20:10
私たちが泊ったロッジと海辺のホテルとの間は
1時間に2本のシャトルバスが運行されています。
島内にはタクシーがないのでこれが宿泊客の唯一の交通手段です。
ロッジからバスで5分のところにラナイ・シティという
島内唯一の町があります。といってもお店は
細長い公園を挟んで両側に20軒くらいあるだけ(写真下)。
その中のマーケット(写真上)で買い物をしていたとき
「日本の方ですか」という声がしました。
ミッシェルという女性で話してみると座間の米軍キャンプに
4年いたことのことですが、その割にはとても滑らかな日本語です。
町のギャラリーに勤めているので是非寄って、と言われたので
訪ねてみました。(写真上)そこで紹介された店主のマイク・キャロルは
シカゴ出身の画家で、10年位前にラナイ島に遊びに来て
その魅力に取りつかれ、シカゴを引き払って移住したそうです。
いつも笑顔を絶やさないたいへん温和そうな人柄です。
その翌日ホテルの一角で絵画の展示即売会が行なわれているので
覗いてみるとそこにいたのは、にこやかなキャロルさんでした。
最後の日はジープを借りてドライブしようと思いましたが
前夜に雨が降り、大半が舗装されてない島内を走るのは無理なので断念。
そこで地図をよく見ると海辺のホテルから歩けそうなところに
「Sweetheart Rock」というポイントが記されていたので
パラソルの並ぶ砂浜を通り、海沿いに岩場を上がって行きました。
すると急に目の前が断崖になり、その先は大海原が広がる絶景です。
ドライブをしなくてもこんな風景が見られるとは何と運がいいのでしょう。
また不思議なことは、このような場所に誰もいないのです!
帰ろうと下り始めたところでやっと一組とすれ違いました。
ホテルの宿泊客はここを知らないのでしょうか?
そこに何時間でもいたくなるような素晴しい場所に人が全くいない!
こんな信じがたい島が「ハワイ最後のパラダイス」ラナイ島です。
(社長)
ラナイ島の旅 (1)
- 2009年11月18日 19:01
「ハワイ最後のパラダイス」と呼ばれている
ラナイ島は、大きさがホノルルのあるオアフ島の約4分の1で
人口はわずか3,000人の島です。(ちなみにオアフ島は約90万人)
今の環境と全く違うところに短期間でも移動することで
心身ともリフレッシュを図りたいと思い
時間をやり繰りして先週、妻とラナイ島を訪れました。
海辺には「マネレ・ベイ」 山のふもとには「ザ・ロッジ・アット・コエレ」
という2つの素晴しいフォーシーズンズ・リゾートがあるだけで
その他は未開発の原野がほとんどです。
私たちは標高480mの丘にある「ロッジ」の方に泊まりましたが
広大な芝生とノーフォーク・パインという高く空に伸びた松に囲まれ
涼風の吹くこのホテルはまるで高原リゾートのようです。
ガイド付きのハイキングがあったので申込みましたが
参加者は私たちのほかは無く、2m近い身長のジョーの専用ガイドで
ホテルから約2時間のハイキングを楽しみました。
山の頂上近くになると急に視界が開け
マウイ島とモロカイ島が渓谷越しに見えたときの気持ちは
ちょっと言葉には表わせないほどで
ずっとそのままそこにいたい、という感覚に包まれました。
ジョーは私のカメラを見て「自分のと同じCANONだ」と言って
自分のフォトサイトのカードを私にくれました。 →http://joewestphoto.com
翌日ホテルで行なわれたカクテルパーティーに顔を出すと
ホストの一人にジョーがいるのでまずビックリ。
そしてホテルでラナイ島のガイドブックを買ったら、その中に
「フォトグラファー・ジョー」の名を見つけて2度ビックリ。
「ザ・ロッジ・アット・コエレ」を発つ日
三たびエントランスで彼に出会い、一緒に写真を撮りました。
ケンタッキー州出身、大男のジョーはなかなかの紳士でインテリでした。
日本のこれから
- 2009年11月 8日 18:47
昨日ロータリークラブの地区大会が開かれその中で
「日本のこれから」と題した藤原正彦・御茶の水女子大
名誉教授の講演がありました。
藤原さんは2005年に出版した「国家の品格」が
250万部を超える大ベストセラーになったことで有名です。
講演は「いま史上最低の国民が日本を壊している」という
激しい現在の日本の風潮の批判から始まりました。
政治家は国民の要望は聞くな。
国民の目線で政治を行えば国が滅びてしまう。
何故かというと国民は気まぐれであり
国民を圧倒する知性で国民をリードするのが本当の政治家である。
国民投票で95%以上が支持したヒトラーの例や
戦前の「鬼畜米英」が戦後はすっかり民主主義に変った
我々日本人の例を挙げて説明しましたが、その内容の賛否はともかく
これだけストレートな主義主張を最近聞くことは珍しくなりました。
今の大学生に日本はどんな国かを聞いてみると
「恥ずかしい国」と思っている学生が少なくないのには驚くが
歴史的に見て日本の文学、芸術、数学は欧米に引けを取らないどころか
西暦500年から1500年までの1000年間で考えると
その間の日本の数々の文学作品に比べられる世界の文学はわずかしかない。
また数学でも理系の大学生がまず習う「行列式」について言うと
江戸初期に生れた関孝和が独学でその概念を考え出したそうで
調べてみると「微分・積分」についてもヨーロッパより少し前に
彼が一歩手前までたどり着いたことも分かりました。
藤原さんが文部省の審議委員をしていたとき、指導要項に「丁寧な指導」のあとに
「厳しく」の文字を入れたほうがいいと発言したら、大御所の先生が
「厳しくすると児童の心が傷つく」と言われて唖然としたとか。
今の学校の教室には教壇がないそうです。
教壇があると先生が生徒の一段上から見下すことになるから・・・
日本のこれから、私たちはもう少し自信と誇りを持っても良いのではないでしょうか。
(社長)
- Search